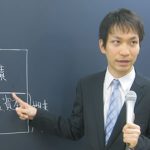各科目の講義を、複数の講師が担当
CPA会計学院では、自分に合った講師を選んで講義を受講することができます。
講師一人ひとりが、受講生が最も理解しやすいと思う講義を行っています。
同じ科目でも様々なスタイルの講義が実施されており、自分にとって分かりやすいと思う講義を選ぶことができるので、早く理解を深めることができます。
【合格者の声】
- 「CPAには様々な講師がおり、自分に合った教え方の講師を選んで講義を受講できるところに魅力を感じました」(女性合格者・在学中に合格・通学講座で合格・一発合格)
- 「自分に合った講師を選べたことで、ストレスなくインプット段階を終えることができました」(男性合格者・通信講座で合格・一発合格)
- 「CPAでは各教科に複数の講師がおり、その中から自分に合った講師を選べるようになっています。そのため自分のレベルに合わせて講師を選ぶことができ、学力を上げる上で非常に助けになりました」(男性合格者・在学中に合格・通学講座で合格・一発合格)
佐藤 大輔 講師
財務会計論(理論)
徹底的に、「深い理解」と「論点の網羅性」を追求した講義近年の短答式/論文式試験では、「会計の基本的な考え方を問う問題」と「会計基準に記載されている規定の内容(詳細な内容を含む)を問う問題」の双方が出題される傾向に…
渡辺 克己 講師
財務会計論
財務会計論は短答式試験・論文式試験ともに最も配点の高い科目です。その重要な科目を預かる立場として、講義は言うまでもありませんが、教材の作成や答練・模試の作問に至るまで、すべてにおいて真剣勝負…
池邉 宗行 講師
管理会計論
問題集や答練の問題は解けるが、本試験の問題は解けない。管理会計論を苦手にする受験生の特徴です。本試験で合格点を取るためには、その問題の何を理解し、押さえる必要があるのか。私の教材、講義ではこの点にフォ…
松本 裕紀 講師
監査論
監査論は地味で一見難解な科目です。私も正直言えば、受験生の頃、監査論を苦手にしていた時期がありました。そんな私だからこそ断言しますが、監査論は決して難しくない。いくつかの大筋さえ理解してしまえば、あと…
植田 有祐 講師
財務会計論・管理会計論・経営学
心に残る講義すべての担当科目で、「心に残る講義」、「皆さんが公認会計士になった後も思い出してもらえる講義」を展開します。私の講義では、「覚えて!」とは絶対に言いません。「理解して!」と言います。どうしても覚えないと…
髙野 大希 講師
財務会計論・企業法・租税法
公認会計士試験合格の最大のカギは、コツコツと学習を継続することです。莫大な試験範囲をカリキュラム通りにこなしていき、毎回丁寧に復習する。簡単に聞こえますが、これが最…
伏見 遼 講師

企業法
条文や論点のイメージ付けと趣旨の理解を徹底的に行うので、理解という土台に基づいた暗記をすることが可能となります。そのため、長期間知識を定着させることができ、さらに応用的な問題にも対応することができるようになります
永田 武士 講師
経営学
経営学は、公認会計士試験の中で最も学習量の少ない科目なので、少ない時間でより多くの点数を稼ぐことができます。特に、財務管理(計算科目)は近年、基本的な問題が多く出題されており、こちらで満点近く取ることも可能なので、コストパフォーマンスの非常に高い科目だと思います。
林 学 講師
管理会計論
「安定して合格点以上を取る」ことのできる講義近年の本試験における管理会計論は、一部の難解な問題を除いて、理論問題については得点しやすい問題が多く出題されています。一方、計算問題については、問題文の読み取りが難しい問題や…
矢野 友貴 講師

管理会計論・経営学
全体像を俯瞰する「論点マップ」 管理会計論も経営学も、ともすれば各論点を切り離してしまうような視野の狭い学習に陥ってしまいます。私の講義では、各章の論点同士の繋がりを紙一枚にビジュアル化した「論点マップ」というオリジナル…
青木 拓志 講師
企業法
法律答案の「型」を知る!法律答案には「型」があります。この型を守るか守らないかで点数が変わります。まずはこの「型」を学びます。条文を重視!本試験問題を検討すると、いわゆる「論点」の問題は4分の1しか出題されていませ…
若杉 咲良 講師
企業法
直前期の自習につながる講義短答対策は、結局は自習量がモノをいいます。インプット素材(レギュラーテキストやコンサマ)とアウトプット素材(短答対策問題集)を何度も回転させながら、知識の穴を見付けては埋めていくという作業を繰…
全教科複数の講師で万全サポート